2月1日(日曜日)に、愛媛大学で、「えひめサイエンスチャレンジ2025」を実施しました。
一般部門に42チーム、プログラム参加部門に20チームの合計62チームの参加があり、過去最大規模での開催となりました。
生徒がこれまで取り組んできた研究の成果を発表し、分かりやすく伝える力や、科学的な視点から議論する力を高める貴重な機会となりました。
発表された研究内容は、数学・情報領域、物理領域、化学領域、生物領域、地学領域など多岐にわたり、どの発表も、レベルの高い素晴らしい発表でした。
入賞した研究は以下のとおりです。
【一般部門】
最優秀賞
愛媛県立長浜高等学校 「ミナミトビハゼの体表粘液における物理的・化学的防御の検証~水陸両用見えないバリアの秘密~」
優秀賞
愛媛県立三島高等学校 「水流中に現れる水球の正体」
愛媛県立松山南高等学校 「光が魅せる逃げ水の不思議-地面の凹凸と陽炎の影響-」
愛媛県立松山南高等学校 「回転する縄から発生する風切り音の研究」
愛媛県高等学校教育研究会数学部会長賞
愛媛県立新居浜西高等学校 「ヨーヨーの運動における力学的エネルギーの解析」
愛媛県高等学校教育研究会理科部会長賞
愛媛県立三島高等学校 「誰でも簡単に三不粘を作れる新商品の開発」
努力賞
愛媛県立上浮穴高等学校 「バイオ由来高吸水性ポリマーの合成と評価~脱水条件に着目して~」
愛媛県立長浜高等学校 「マダコの鏡像自己認知~タコは自分がわかるのか~」
愛媛大学附属高等学校 「希少種マツカサガイの一時避難方法の検討」
【プログラム参加部門】
優秀賞
愛媛県立松山中央高等学校 「識別ケイソウ群法による里山と都市の水質比較調査」
愛媛県立北宇和高等学校 「途上国における簡易飲み水除菌法の開発~実用化を目指して~」
愛媛県立宇和島南中等教育学校 「不思議に浮かぶドーナツ円板」
奨励賞
愛媛県立川之江高等学校 「「Hit&Blow」の勝率を上げる方法」
愛媛県立三島高等学校 「おにぎりの冷え方は冷めゆく星と一緒なのか」
愛媛県立新居浜東高等学校 「7パズル(2行4列)を解く最短スライド数の最大値の考察」
愛媛県立新居浜西高等学校 「ATAホイル法による一般細菌の吸着実験の研究」
愛媛県立新居浜南高等学校 「ルービックキューブの1面を揃える最短数の変容」
愛媛県立西条高等学校 「電子レンジを活用したセスキ炭酸ナトリウムの簡便な高収率化」
愛媛県立丹原高等学校 「遺伝的浮動の数学的シミュレーション」
愛媛県立丹原高等学校 「TAKENOWA+(plus) -"竹×○○" に関する研究-」
愛媛県立丹原高等学校 「気孔の観察から分かること~スス付着モデルを用いた気孔機能の研究~」
愛媛県立今治西高等学校 「発熱したスマホの冷やし方」
愛媛県立弓削高等学校 「中央構造線断層帯の影響によってできる地形の考察」
愛媛県立松山南高等学校 「粘性流体の粒子を液体に滴下した時の拡散の様子について」
愛媛県立松山南高等学校 「カワリヌマエビ属における背景色が滞在行動に及ぼす影響」
愛媛県立松山南高等学校 「愛媛県におけるコガタノゲンゴロウの増加の要因と生態系に与える影響について」
愛媛県立松山中央高等学校 「振り子の力学的エネルギーと衝突が及ぼす影響」
愛媛県立松山中央高等学校 「日焼け止めによる紫外線防御効果の検証」
愛媛県立松山中央高等学校 「水流の刺激がテイレギの辛みに与える影響」
愛媛県立大洲高等学校 「大洲市の武田川を中心とした水質調査から考察するプラナリア生育環境」
愛媛県立野村高等学校 「和算と高校数学を活用した現代解の探究 ~雑題(大西佐兵衛著)に触れて~」
愛媛県立宇和島東高等学校 「アコヤガイの廃貝殻を吸着材へ! ~キレート滴定を用いた吸着力の検証~」
愛媛県立宇和島東高等学校 「災害時の井戸水の活用に向けて」
愛媛県立宇和島東高等学校 「宇和島市に棲む新種を探せ~宇和島市は地下水生昆虫の聖地!?~」







2月2日(日曜日)に、愛媛大学で、「えひめサイエンスチャレンジ2024」を実施しました。
生徒がこれまで取り組んできた研究の成果を発表し、分かりやすく聞き手に伝える力や、科学的な視点で考え議論する力を高める貴重な機会となりました。
発表された研究内容は、数学・情報領域、物理領域、化学領域、生物領域、地学領域など多岐にわたり、どの発表も、熱意あふれる素晴らしい内容でした。発表後には質疑応答が行われ、発表者と聞き手にとって、有意義な時間となりました。入賞した研究は以下のとおりです。
【一般部門】
最優秀賞
愛媛県立松山南高等学校 「下敷き変形時における音の発生原理」
優秀賞
愛媛県立三島高等学校 「付箋をめくるとなぜ紙がロールするのか」
愛媛県立西条高等学校 「CO2濃度測定における湿度補正の有効性と自作デバイスへの実装」
愛媛県立長浜高等学校 「マダコの鏡像自己認知 ~タコは自分が分かるのか~」
愛媛県高等学校教育研究会数学部会長賞
愛媛県立長浜高等学校 「サンゴガニは攻撃対象を何で判断しているのか~視覚か嗅覚か~」
愛媛県高等学校教育研究会理科部会長賞
愛媛県立松山中央高等学校 「炭酸カルシウムが海洋酸性化に与える影響」
努力賞
愛媛県立丹原高等学校 「”竹輪(TAKENOWA)”~竹の繊維化とその魅力UPに向けた研究~」
愛媛県立宇和島東高等学校 「アコヤガイの貝殻による重金属吸着の条件検討~廃液ゼロを目指して~」
愛媛県立宇和島東高等学校 「トキワバイカツツジの生育に適した光条件と土壌の分析」
【プログラム参加部門】
優秀賞
愛媛県立新居浜南高等学校 「新居浜で観測された複数の漏斗雲の発生原因―フォグマシーンを用いた竜巻の再現実験―」
愛媛県立長浜高等学校 「ミズクラゲのメデューサからメデューサへの再生要因」
愛媛県立宇和島東高等学校 「垂直差し込み式剛体振り子の地震動に対する応答~吊り照明の安全性向上を目指して~」
奨励賞
愛媛県立川之江高等学校 「愛媛の算額における作図方法の研究」
愛媛県立三島高等学校 「温度上昇率からケン化価を推定する手法の開発」
愛媛県立新居浜東高等学校 「再現可能な光沢のある銅鏡を生成する方法ーホルマリンの還元作用を活用してー」
愛媛県立新居浜西高等学校 「クスノキのダニ室の秘密に迫る~葉の大きさとダニ室の大きさの関係~」
愛媛県立西条高等学校 「和算を使った問題作成」
愛媛県立西条高等学校 「促進剤炭酸ナトリウムを用いた輝安鉱の人工合成~輝安鉱巨大化の謎の探究~」
愛媛県立丹原高等学校 「水質浄化に向けて~使用済みカイロと竹パウダーを用いて~」
愛媛県立今治西高等学校 「アルミホイルを用いた汚染物質吸着に関する研究」
愛媛県立今治西高等学校 「還元糖検出の最適条件についての研究」
愛媛県立今治西高等学校 「今治市内の外来性ウズムシの増加と自切速度の関係性について」
愛媛県立松山北高等学校 「愛媛の石で温まりたい~岩石蓄熱の比較~」
愛媛県立松山中央高等学校 「改変アルミホイルを用いた吸着特性の最適条件」
愛媛県立松山中央高等学校 「テイレギの辛さを決定づける要因について」
愛媛県立松山中央高等学校 「愛媛県の都市部と郊外におけるミナミメダカの生息状況の比較と現状」
愛媛県立八幡浜高等学校 「船外機における温度差発電」
愛媛県立川之石高等学校 「和算の解法と和算文化の研究~『算法新書』の解読を通して~」
愛媛県立宇和島東高等学校 「食材の“凍結”による味の変化~ヒトの味覚で測る官能評価~」
愛媛県立北宇和高等学校 「大腸菌吸着ATAホイル作成におけるカルシウム系化合物使用の検討」
愛媛県立今治東中等教育学校 「今治東中等教育学校の学校魅力化が地域社会へ与える経済効果の分析」


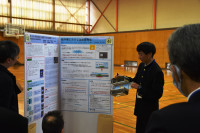




このたび、愛媛大学 向 平和 教授と、えひめサイエンスリーダースキルアッププログラム企画運営会議が、日本科学教育学会「科学教育実践賞」 を受賞しました。本賞は、科学教育の実践研究において顕著な業績や功績を上げた団体・個人に贈られるものです。
本プログラムは、愛媛大学と愛媛県教育委員会、愛媛県高等学校教育研究会数学部会、理科部会が連携したプログラムです。これまで、課題研究活動を通じて、生徒の科学的思考力・判断力・表現力等を養うとともに、科学に対する興味・関心を育てること、また、教員の課題研究における指導力の向上に取り組んできました。今回の受賞は、これまで10年間の活動が評価された結果であり、関係者一同、大変光栄に思っています。
これからも、より多くの生徒が科学の魅力に触れ、未来の科学者・技術者として成長できる環境を提供していきます。
